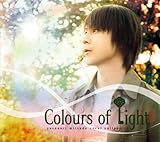――ファンタズマゴリア――
走馬灯のように 次々と移ろいゆく 幻想の中で
プロフィール
管理人:波華
観劇好き。主に狂言、歌舞伎、日本舞踊、大衆演劇、落語などをよく観ます。大蔵流茂山千五郎家、尾上菊之助さん、中村勘九郎さん、尾上菊之丞さん、橘菊太郎劇団、劇団花吹雪、などがお気に入り。
現代演劇で最大のお気に入りは花組芝居。その他、大中小気になった劇団を観に行きます。
日本舞踊のお稽古をしています。
たまに着物や歌やゲーム(DQ,FF)の話題も。
連絡先 e_yassie@yahoo.co.jp
現代演劇で最大のお気に入りは花組芝居。その他、大中小気になった劇団を観に行きます。
日本舞踊のお稽古をしています。
たまに着物や歌やゲーム(DQ,FF)の話題も。
連絡先 e_yassie@yahoo.co.jp
鑑賞予定
最新記事
最新コメント
たつみ演劇BOX公演@しのはら演芸場 2/11夜⇒
波華@管理人[03/14]
たつみ演劇BOX公演@しのはら演芸場 2/11夜⇒
moto[03/10]
たつみ演劇BOX公演@浅草木馬館 1/17夜⇒
波華@管理人[02/08]
たつみ演劇BOX公演@浅草木馬館 1/17夜⇒
moto[02/06]
菊花の契り⇒
波華@管理人[11/19]
菊花の契り⇒
くりみ[10/18]
遅くなりましたが、感想 「鼓の家」⇒
波華@管理人[07/04]
遅くなりましたが、感想 「鼓の家」⇒
蜂須賀承能[07/04]
劇団新感線「蒼の乱」⇒
波華@管理人[04/25]
劇団新感線「蒼の乱」⇒
moto[04/24]
カテゴリー
アーカイブ
2022年03月
(1)
2022年02月
(1)
2022年01月
(1)
2021年12月
(1)
2021年11月
(1)
2021年10月
(1)
2021年09月
(1)
2021年08月
(1)
2021年07月
(1)
2021年06月
(1)
2021年04月
(3)
2021年03月
(1)
2021年02月
(1)
2021年01月
(1)
2020年12月
(1)
2020年11月
(1)
2020年10月
(1)
2020年09月
(1)
2020年08月
(1)
2020年07月
(1)
2020年05月
(1)
2020年04月
(2)
2020年02月
(1)
2020年01月
(1)
2019年12月
(1)
2019年11月
(1)
2019年10月
(1)
2019年09月
(1)
2019年08月
(2)
2019年07月
(1)
2019年06月
(1)
2019年05月
(1)
2019年04月
(1)
2019年03月
(2)
2019年01月
(1)
2018年12月
(1)
2018年11月
(1)
2018年09月
(2)
2018年08月
(1)
2018年07月
(1)
2018年06月
(1)
2018年05月
(1)
2018年04月
(1)
2018年03月
(1)
2018年02月
(1)
2018年01月
(1)
2017年11月
(2)
2017年10月
(1)
2017年09月
(1)
2017年08月
(1)
2017年07月
(1)
2017年06月
(1)
2017年05月
(1)
2017年04月
(1)
2017年03月
(1)
2017年02月
(1)
2017年01月
(1)
2016年12月
(1)
2016年11月
(1)
2016年10月
(1)
2016年09月
(1)
2016年08月
(1)
2016年07月
(1)
2016年06月
(1)
2016年05月
(1)
2016年04月
(1)
2016年03月
(1)
2016年02月
(1)
2016年01月
(2)
2015年12月
(2)
2015年10月
(1)
2015年09月
(4)
2015年08月
(1)
2015年03月
(1)
2015年02月
(2)
2015年01月
(5)
2014年12月
(1)
2014年11月
(1)
2014年10月
(7)
2014年09月
(6)
2014年08月
(21)
2014年07月
(11)
2014年06月
(22)
2014年05月
(19)
2014年04月
(6)
2014年03月
(11)
2014年02月
(3)
2014年01月
(22)
2013年12月
(2)
2013年11月
(3)
2013年10月
(7)
2013年09月
(5)
2013年08月
(15)
2013年07月
(17)
2013年06月
(4)
2013年05月
(19)
2013年04月
(6)
2013年03月
(12)
2013年02月
(20)
2013年01月
(21)
2012年12月
(18)
2012年11月
(19)
2012年10月
(15)
2012年09月
(19)
2012年08月
(8)
2012年07月
(32)
2012年06月
(10)
2012年05月
(20)
2012年04月
(11)
2012年03月
(15)
2012年02月
(22)
2012年01月
(27)
2011年12月
(10)
2011年11月
(18)
2011年10月
(18)
2011年09月
(20)
2011年08月
(21)
2011年07月
(15)
2011年06月
(14)
2011年05月
(23)
2011年04月
(7)
2011年03月
(13)
2011年02月
(9)
2011年01月
(10)
2010年12月
(16)
2010年11月
(18)
2010年10月
(19)
2010年09月
(11)
2010年08月
(16)
2010年07月
(26)
2010年06月
(26)
2010年05月
(26)
2010年04月
(26)
2010年03月
(17)
2010年02月
(11)
2010年01月
(24)
2009年12月
(23)
2009年11月
(10)
2009年10月
(17)
2009年09月
(16)
2009年08月
(12)
2009年07月
(23)
2009年06月
(18)
2009年05月
(13)
2009年04月
(15)
2009年03月
(18)
2009年02月
(6)
2009年01月
(22)
2008年12月
(19)
2008年11月
(20)
2008年10月
(27)
2008年09月
(20)
2008年08月
(20)
2008年07月
(24)
2008年06月
(16)
2008年05月
(22)
2008年04月
(17)
2008年03月
(18)
2008年02月
(22)
2008年01月
(26)
2007年12月
(18)
2007年11月
(13)
2007年10月
(22)
2007年09月
(21)
2007年08月
(11)
2007年07月
(19)
2007年06月
(10)
2007年05月
(18)
2007年04月
(16)
2007年03月
(1)
2007年02月
(5)
2007年01月
(13)
2006年12月
(5)
2006年11月
(11)
2006年10月
(12)
2006年09月
(9)
2006年08月
(18)
2006年07月
(14)
2006年06月
(15)
2006年05月
(15)
2006年04月
(24)
2006年03月
(21)
2006年02月
(17)
2006年01月
(19)
2005年12月
(14)
2005年11月
(16)
2005年10月
(17)
2005年09月
(18)
2005年08月
(17)
2005年07月
(9)
2005年06月
(17)
2005年05月
(27)
2005年04月
(23)
2005年03月
(17)
2005年02月
(18)
2005年01月
(25)
2004年12月
(20)
2004年11月
(14)
2004年10月
(21)
2004年09月
(18)
更新リスト
カウンター
ブログ内検索
カレンダー
アクセス解析
Ad
傳 -未来へ- vol.2 能楽 レポその1
2005年03月24日(木) 14:15:20
今回は運良く、一列目という良席。下手側でした。
舞台は中央が前にせり出した形で、脇正面とその反対側にも少しだけ席ができていました。バックスクリーンには写真のように「傳」の字が映し出されていました。
素囃子『道成寺組曲』 笛:田中義和 小鼓:成田達志 大鼓:亀井広忠 太鼓:大川典良
レクチャー&ワークショップ『囃子・謡・狂言』亀井広忠・大島輝久・茂山逸平
狂言『芯奪』(しんばい) 主人:茂山逸平 太郎冠者:茂山宗彦 通人:茂山童司
舞囃子『鞍馬天狗』シテ:狩野了一 地謡:金子敬一郎 佐々木多門 大島輝久
笛:田中義和 小鼓:成田達志 大鼓:亀井広忠 太鼓:大川典良
「道成寺組曲」
素囃子なので、囃子方が舞台前方にずずいっと出てきてくれたのが嬉しかった。下手側だから広忠さんが近い~!こんなに近くで見たのは初めてかもしれないです。
最初は何の曲を演奏するのか忘れていたのですが、曲が始まってしばらくして、聞いたことあるな、と。ビクターの亀井さんCDに収録されているので覚えていたようです。
前半に少し出てきた小鼓一調の緊迫した部分は乱拍子でしょうか。ぐっと息をこらえて見つめていました。それから後半の手数が立て込んできて盛り上がるところも圧倒されます。太鼓を打つときの独特の型ってやっぱりきれいですねー。
曲が進むにつれて赤くなっていく広忠さんの手も、額から流れる汗も、ばっちり見えましたよ~。他の3人の囃子方はグレーに縞模様の袴なのに、広忠さんだけ藤色の綺麗な色の袴だったのも素敵でした!
ところで私は能の「道成寺」は見たことが無いので絵が浮かばなかったのですが、代わりに歌舞伎の「娘道成寺」を思い浮かべながら聞いてしまっていました(^^;
音響ですけど、やっぱり能楽堂の響きとは若干違うように思います。なんでだろ、能楽堂みたいに屋根が無いからかなぁ。天井が高い分、響きが多少散ってしまって、あまり残響が無いように聞こえました。まぁ、気になったのは初めだけで、演奏に聞き入ってしまってからは気にならなくなりましたけど。
それよりミキサールームから人の声が思い切り聞こえてきたのには腹が立ちました。最前列まで聞こえてくるなんて!ありえない。音を魅せる舞台で雑音を聴かされることほど、腹立たしいことはない。演奏終了後にミキサールームを睨んでいる人が多かった。私も睨みつけてやりましたよ。ホールスタッフを務める自覚があるのか疑わしいです。
レクチャー&ワークショップ
まず、逸平さん登場~!黒紋付です。まず、能とは何か、狂言とは何かについて簡単に解説。スライドで能楽堂の見取り図を見せて解説。それからアシスタントの宗彦さんを呼んで、狂言の型の実演。笑いの型、道行、扉を開ける、酒宴などを実演してくれました。真面目なように見えてどこかしら可笑しいもっぴは相変わらずという感じ(笑)
シテ方の大島さんも呼んで、「笑う」「泣く」の2つの型について、能と狂言の型の違いを見せてくれたのがとても興味深かったです。能の泣く型は観たことがありましたが、笑いの型は初めてちゃんと見たような気がします。「笑う」というより「嬉しい、晴れ晴れとした、喜んでいるさま」というほうがしっくりくるかもしれません。狂言だと「はぁー はぁー は は は は 」と声を出しながら顔を徐々に上げていきますが、能だと言葉は発せずに扇を大きく振り上げながら体を上向きに反らせていくという感じでしょうか。泣く方は、手のひらを目の下にあてがって、涙を受けている形にして顔を下に向ける、という感じ。
そういえば、狂言の道行きは能舞台を大きく三角に描いて一周しますが、能の場合はほんの一歩で道行を表していました、確か。こうやって見ると、能と狂言はだいぶ違うなぁと思いました。
狂言のワークショップは、「笑い」の型の実演でした。狂言のワークショップといえばだいたいコレですね。
次に囃子の解説。先ほど「道成寺組曲」を演奏してくださった4人が登場し、それぞれの楽器の解説をしてくれました。
まず笛は節の間隔が長い竹を、囲炉裏の上に吊るして煤を付け、籐でぐるぐる巻きにした後に漆で塗り固めてあります。わざわざ音を出しにくい構造になっている分、役者自身のリアリティが音に出る、魂がこもるとのこと。笛の作者によって構造が変わるので、西洋音楽のようにきちんとドレミの音階は出ないものなんですが、なぜか一噌幸弘さんはドレミの音階を出せるらしいんですねー器用ですねー。
小鼓は、子馬のお腹の薄い皮でできています。2枚の皮の間に挟んだ胴は桜の木で、調緒と呼ばれる紐で皮をピンと張っています。
大鼓は、成熟した馬のお尻または背中の硬い皮を使っています。小鼓に比べると随分硬く、乾いた鋭い音が出ます。本番の2,3時間前に楽屋入りして、皮を焙じて乾燥させることで硬い音が出るようになります。
太鼓は、全体は牛の皮で、真ん中に小さく丸く貼り付けてあるのが鹿の皮。太鼓を置く台は後世にできたもので、昔は太鼓を持つ人と太鼓を叩く人の2人がかりだったとか。
次に、「舞働」という曲(?)の実演です。入場時に「舞働」の譜面らしきものをもらったのですが(しかも亀井さんの手書きっぽい)、こんなのを初めて見た私にとっては、縦に読むのか横に読むのかさえ分からなかった…読み方を教えて欲しかったな。
囃子方の申し合わせの時には楽器を使わずに扇と声だけで合わせるそうです。その楽器を使わないバージョンと楽器を使うバージョンの「舞働」を実演してもらいました。
その次は、大鼓と小鼓だけで演奏する「三地」(ミツヂ)を使ったワークショップ。会場のお客さんを大鼓役と小鼓役の二つに分けて、手拍子と声だけで、成田さん広忠さんと一緒に実演。私は大鼓役でした。ここでやっと、譜面は縦に読むらしいと分かりました。縦棒や三角や白丸は、叩き方の違いなんでしょうね。小鼓で言う「チ」「タ」「プ」「ポ」の違い。
しかし、これはけっこう難しい!真似するだけなんだけど、声の出し方とかタイミングとかなかなか掴めなくて。3回くらいやりましたけど、難しいものだということは良く分かりました(^^;
そして大島さんの謡の解説。「鞍馬天狗」の謡の一部を使ったワークショップでした。謡本のコピーを見ながらの実演でした。詞章の横についているゴマ点は節を表していて、形によって「ユリ節」とか「ヒキ」とか「マワシ節」とかを表しているとのこと。と言われてもなんだか良く分かりません(^^;
大島さん自身も、稽古は3歳くらいから始めているけれど、最初から謡本を見ながら稽古したわけではなく師匠からの口伝なので、謡本の読み方を知ったのは随分後になってからだとか。私らは謡に関しては3歳児も同然ですから、大島さんの真似をするしかありません。
というわけで、大島さんについて一句ごとに練習。はわ~これもなかなか難しい!音低いしね…。2回一緒に謡って、終了。「(大島さん)最初は誰も謡ってくれないんじゃないかと気が気じゃなかった」そうですが、最後には一応、お褒めのお言葉を頂きましたよ。
そして、休憩。
休憩中に、ロビーで、なななんと青楓さん発見!ギャー
見に来てないかなー見に来てるといいなーと妄想しているうちにすっかり見に来てくれている気分になっていた私の願いが届いたのか。
もぉドキドキ。
おかげで休憩が終わってもしばらく夢うつつでしたよ…。
後半は、後日!
素囃子なので、囃子方が舞台前方にずずいっと出てきてくれたのが嬉しかった。下手側だから広忠さんが近い~!こんなに近くで見たのは初めてかもしれないです。
最初は何の曲を演奏するのか忘れていたのですが、曲が始まってしばらくして、聞いたことあるな、と。ビクターの亀井さんCDに収録されているので覚えていたようです。
前半に少し出てきた小鼓一調の緊迫した部分は乱拍子でしょうか。ぐっと息をこらえて見つめていました。それから後半の手数が立て込んできて盛り上がるところも圧倒されます。太鼓を打つときの独特の型ってやっぱりきれいですねー。
曲が進むにつれて赤くなっていく広忠さんの手も、額から流れる汗も、ばっちり見えましたよ~。他の3人の囃子方はグレーに縞模様の袴なのに、広忠さんだけ藤色の綺麗な色の袴だったのも素敵でした!
ところで私は能の「道成寺」は見たことが無いので絵が浮かばなかったのですが、代わりに歌舞伎の「娘道成寺」を思い浮かべながら聞いてしまっていました(^^;
音響ですけど、やっぱり能楽堂の響きとは若干違うように思います。なんでだろ、能楽堂みたいに屋根が無いからかなぁ。天井が高い分、響きが多少散ってしまって、あまり残響が無いように聞こえました。まぁ、気になったのは初めだけで、演奏に聞き入ってしまってからは気にならなくなりましたけど。
それよりミキサールームから人の声が思い切り聞こえてきたのには腹が立ちました。最前列まで聞こえてくるなんて!ありえない。音を魅せる舞台で雑音を聴かされることほど、腹立たしいことはない。演奏終了後にミキサールームを睨んでいる人が多かった。私も睨みつけてやりましたよ。ホールスタッフを務める自覚があるのか疑わしいです。
レクチャー&ワークショップ
まず、逸平さん登場~!黒紋付です。まず、能とは何か、狂言とは何かについて簡単に解説。スライドで能楽堂の見取り図を見せて解説。それからアシスタントの宗彦さんを呼んで、狂言の型の実演。笑いの型、道行、扉を開ける、酒宴などを実演してくれました。真面目なように見えてどこかしら可笑しいもっぴは相変わらずという感じ(笑)
シテ方の大島さんも呼んで、「笑う」「泣く」の2つの型について、能と狂言の型の違いを見せてくれたのがとても興味深かったです。能の泣く型は観たことがありましたが、笑いの型は初めてちゃんと見たような気がします。「笑う」というより「嬉しい、晴れ晴れとした、喜んでいるさま」というほうがしっくりくるかもしれません。狂言だと「はぁー はぁー は は は は 」と声を出しながら顔を徐々に上げていきますが、能だと言葉は発せずに扇を大きく振り上げながら体を上向きに反らせていくという感じでしょうか。泣く方は、手のひらを目の下にあてがって、涙を受けている形にして顔を下に向ける、という感じ。
そういえば、狂言の道行きは能舞台を大きく三角に描いて一周しますが、能の場合はほんの一歩で道行を表していました、確か。こうやって見ると、能と狂言はだいぶ違うなぁと思いました。
狂言のワークショップは、「笑い」の型の実演でした。狂言のワークショップといえばだいたいコレですね。
次に囃子の解説。先ほど「道成寺組曲」を演奏してくださった4人が登場し、それぞれの楽器の解説をしてくれました。
まず笛は節の間隔が長い竹を、囲炉裏の上に吊るして煤を付け、籐でぐるぐる巻きにした後に漆で塗り固めてあります。わざわざ音を出しにくい構造になっている分、役者自身のリアリティが音に出る、魂がこもるとのこと。笛の作者によって構造が変わるので、西洋音楽のようにきちんとドレミの音階は出ないものなんですが、なぜか一噌幸弘さんはドレミの音階を出せるらしいんですねー器用ですねー。
小鼓は、子馬のお腹の薄い皮でできています。2枚の皮の間に挟んだ胴は桜の木で、調緒と呼ばれる紐で皮をピンと張っています。
大鼓は、成熟した馬のお尻または背中の硬い皮を使っています。小鼓に比べると随分硬く、乾いた鋭い音が出ます。本番の2,3時間前に楽屋入りして、皮を焙じて乾燥させることで硬い音が出るようになります。
太鼓は、全体は牛の皮で、真ん中に小さく丸く貼り付けてあるのが鹿の皮。太鼓を置く台は後世にできたもので、昔は太鼓を持つ人と太鼓を叩く人の2人がかりだったとか。
次に、「舞働」という曲(?)の実演です。入場時に「舞働」の譜面らしきものをもらったのですが(しかも亀井さんの手書きっぽい)、こんなのを初めて見た私にとっては、縦に読むのか横に読むのかさえ分からなかった…読み方を教えて欲しかったな。
囃子方の申し合わせの時には楽器を使わずに扇と声だけで合わせるそうです。その楽器を使わないバージョンと楽器を使うバージョンの「舞働」を実演してもらいました。
その次は、大鼓と小鼓だけで演奏する「三地」(ミツヂ)を使ったワークショップ。会場のお客さんを大鼓役と小鼓役の二つに分けて、手拍子と声だけで、成田さん広忠さんと一緒に実演。私は大鼓役でした。ここでやっと、譜面は縦に読むらしいと分かりました。縦棒や三角や白丸は、叩き方の違いなんでしょうね。小鼓で言う「チ」「タ」「プ」「ポ」の違い。
しかし、これはけっこう難しい!真似するだけなんだけど、声の出し方とかタイミングとかなかなか掴めなくて。3回くらいやりましたけど、難しいものだということは良く分かりました(^^;
そして大島さんの謡の解説。「鞍馬天狗」の謡の一部を使ったワークショップでした。謡本のコピーを見ながらの実演でした。詞章の横についているゴマ点は節を表していて、形によって「ユリ節」とか「ヒキ」とか「マワシ節」とかを表しているとのこと。と言われてもなんだか良く分かりません(^^;
大島さん自身も、稽古は3歳くらいから始めているけれど、最初から謡本を見ながら稽古したわけではなく師匠からの口伝なので、謡本の読み方を知ったのは随分後になってからだとか。私らは謡に関しては3歳児も同然ですから、大島さんの真似をするしかありません。
というわけで、大島さんについて一句ごとに練習。はわ~これもなかなか難しい!音低いしね…。2回一緒に謡って、終了。「(大島さん)最初は誰も謡ってくれないんじゃないかと気が気じゃなかった」そうですが、最後には一応、お褒めのお言葉を頂きましたよ。
そして、休憩。
休憩中に、ロビーで、なななんと青楓さん発見!ギャー
見に来てないかなー見に来てるといいなーと妄想しているうちにすっかり見に来てくれている気分になっていた私の願いが届いたのか。
もぉドキドキ。
おかげで休憩が終わってもしばらく夢うつつでしたよ…。
後半は、後日!
PR
コメント
楽しそうですねー!
私も行ってみたかったです(笑)
私も昨年ホール能で最前列の席で見た時、広忠師、源次郎師の大小でしたが、新作能で演出が能楽堂とは違うし、囃子方が常とは違う位置で、ホールによくある背の低い柱の陰に源次郎師が隠れ・・・ということがありました。(広忠さんは目の前でしたが♪)最前列も、良かれと思って取っても、疲れるし、全体見えないし、ストレス溜まりました(笑)やっぱ、能は能楽堂で見るべきものだな・・・と思いました・・・。
レクチャー&ワークショップも面白そうですね!
三地は、最初にこれの練習をいっぱいしましたよ・・・。あとツヅケという手と三地、この二つが基本なのですが、苦労しました(笑)
大鼓と太鼓は体験したことがないのですが、笛は・・・音出ないし、一生懸命吹いたら酸欠になりました(苦笑)
私も行ってみたかったです(笑)
私も昨年ホール能で最前列の席で見た時、広忠師、源次郎師の大小でしたが、新作能で演出が能楽堂とは違うし、囃子方が常とは違う位置で、ホールによくある背の低い柱の陰に源次郎師が隠れ・・・ということがありました。(広忠さんは目の前でしたが♪)最前列も、良かれと思って取っても、疲れるし、全体見えないし、ストレス溜まりました(笑)やっぱ、能は能楽堂で見るべきものだな・・・と思いました・・・。
レクチャー&ワークショップも面白そうですね!
三地は、最初にこれの練習をいっぱいしましたよ・・・。あとツヅケという手と三地、この二つが基本なのですが、苦労しました(笑)
大鼓と太鼓は体験したことがないのですが、笛は・・・音出ないし、一生懸命吹いたら酸欠になりました(苦笑)
早々のレポありがとうございます!お出かけになるまえに書き込みしようとしたのですが、何回やってもうけいれられませんでした。
でも、こんなに早く様子がきけてとてもうれしく思います。
行けなかった私には本当にありがたいものです。
始めに写真もつけていただいて本当に素敵です!
何回も読みかえし自分も行った気になれました。
私も先日せぬひまのワークショップに行ってきました。
舞台というより、六畳の和室を二室くっつけてある部屋の玄関にお客用の椅子が並んだようなところでした(すいません、説明へたで)。
私は一番前の席に着けたのでお囃子がもうすごい迫力でした!
もちろん小鼓は先日お話した、吉坂一郎氏でした。
こちらも道成寺をしていただけました、ものすごい緊張感で私は目眩さえ起こしそうになりました。
終演後は、囃子方のみなさんと懇親会がありみんなでお茶をしながら様々な質問をぶつけました。どの質問にもとても丁寧にお答えいただき大満足です。
お話がそれてしまいましたが、後半のレポ楽しみに待っています。
でも、こんなに早く様子がきけてとてもうれしく思います。
行けなかった私には本当にありがたいものです。
始めに写真もつけていただいて本当に素敵です!
何回も読みかえし自分も行った気になれました。
私も先日せぬひまのワークショップに行ってきました。
舞台というより、六畳の和室を二室くっつけてある部屋の玄関にお客用の椅子が並んだようなところでした(すいません、説明へたで)。
私は一番前の席に着けたのでお囃子がもうすごい迫力でした!
もちろん小鼓は先日お話した、吉坂一郎氏でした。
こちらも道成寺をしていただけました、ものすごい緊張感で私は目眩さえ起こしそうになりました。
終演後は、囃子方のみなさんと懇親会がありみんなでお茶をしながら様々な質問をぶつけました。どの質問にもとても丁寧にお答えいただき大満足です。
お話がそれてしまいましたが、後半のレポ楽しみに待っています。
こんばんは。
レポお疲れ様です♪ものすごく詳しくて読んでて楽しいレポです!!すげっ!こんなに完結に要点まとめられるもんなんですね、見習わなければ…。(私は煩悩の塊だから^^;)
宗彦さんのあの不可思議な感じはいつものことなのですか?
マジメを作ってる感じがたまらなく可笑しかったんですが(笑)茂山家の方々がお話されるのを聞いたのは初めてでしたから^^
波華さんは1列目だったんですね?良席で羨ましいです!
指先が赤くなるのまで見えたとは!!ドキドキ。
私は真中の列あたりの大鼓レクチャー側でした^^
休憩中にロビーではそんなことがあったとは露知らず、ぼけ~っと座ってました(笑)
もしかして、もしかしてだけれども、休憩後半に最前列あたりで立ってお話されてませんでしたか?
遠目に「この人が波華さんだったりして」と思ったんですが…。とんちんかんなこと言ってたらごめんなさい。
レポお疲れ様です♪ものすごく詳しくて読んでて楽しいレポです!!すげっ!こんなに完結に要点まとめられるもんなんですね、見習わなければ…。(私は煩悩の塊だから^^;)
宗彦さんのあの不可思議な感じはいつものことなのですか?
マジメを作ってる感じがたまらなく可笑しかったんですが(笑)茂山家の方々がお話されるのを聞いたのは初めてでしたから^^
波華さんは1列目だったんですね?良席で羨ましいです!
指先が赤くなるのまで見えたとは!!ドキドキ。
私は真中の列あたりの大鼓レクチャー側でした^^
休憩中にロビーではそんなことがあったとは露知らず、ぼけ~っと座ってました(笑)
もしかして、もしかしてだけれども、休憩後半に最前列あたりで立ってお話されてませんでしたか?
遠目に「この人が波華さんだったりして」と思ったんですが…。とんちんかんなこと言ってたらごめんなさい。
こんばんは。また、お邪魔させていただきました。1月末に「ヲヒヤリ」と「鼓の家」の感想を書きます!と言っておきなながら、2ヶ月もたってしまって・・・。インフルエンザに倒れたり、パソコンも壊れてたりして、カキコミの時期を逸してしましました(言い訳)。すいませんでした。
波華さんも「傳」に行かれたんですね。
ホールの最前列は、かなり近いですよね。私はJ列大鼓側でした。せり出している分かなり近くに感じました。
波華さんのレポはすごいですね。行ってきた私でさえも、そうだったな、と改めてと思い出します。メモを取ったりしているのですか?すごすぎます。ほんと脱帽です。
レクチャーでいただいたピンクのお囃子の譜面は広忠さんの手書きです。広忠さんらしいきっちりと真面目な書体ですよね。私は、受付でもう一部もらっちゃいました。
能楽師さんのお話しや、笑ったお顔など拝見する機会はあまりないので、ほんとに貴重な時間でした。レクチャーは終始和やかで、笑いありで楽しいひと時でした。
この場をお借りして・・・
(お知らせ)
4月15日(金)午後4時から、梅若能楽院会館(東中野)で「こころみの会」というのがあります。こちらもお囃子のお話しと実演、一調、舞囃子などがあります。ご出演は、お囃子は大倉源次郎さん、亀井弘忠さん、助川治さん、松田弘之さん。主催が山村庸子さん、一謡一管には梅若六郎さんもご出演されます。詳しくは梅若六郎(さん)サイトで。
では、後半レポ楽しみにしています!
また、お邪魔させてくださいませ。
波華さんも「傳」に行かれたんですね。
ホールの最前列は、かなり近いですよね。私はJ列大鼓側でした。せり出している分かなり近くに感じました。
波華さんのレポはすごいですね。行ってきた私でさえも、そうだったな、と改めてと思い出します。メモを取ったりしているのですか?すごすぎます。ほんと脱帽です。
レクチャーでいただいたピンクのお囃子の譜面は広忠さんの手書きです。広忠さんらしいきっちりと真面目な書体ですよね。私は、受付でもう一部もらっちゃいました。
能楽師さんのお話しや、笑ったお顔など拝見する機会はあまりないので、ほんとに貴重な時間でした。レクチャーは終始和やかで、笑いありで楽しいひと時でした。
この場をお借りして・・・
(お知らせ)
4月15日(金)午後4時から、梅若能楽院会館(東中野)で「こころみの会」というのがあります。こちらもお囃子のお話しと実演、一調、舞囃子などがあります。ご出演は、お囃子は大倉源次郎さん、亀井弘忠さん、助川治さん、松田弘之さん。主催が山村庸子さん、一謡一管には梅若六郎さんもご出演されます。詳しくは梅若六郎(さん)サイトで。
では、後半レポ楽しみにしています!
また、お邪魔させてくださいませ。
>みゆみゆさん
三地は、囃子の曲の中に一番よく出てくると広忠さんが仰っていて、確かにその後演じられた「鞍馬山」にも何回か出てきました。
譜を見ると簡単そうなんですけど、やっぱり難しいですねぇ。大小お互いが息を合わせて間を作らないといけないからかなぁと思いました。
>舞妓さん
この日記を書いているJugemが調子が悪く、投稿されたコメントがすぐに画面に反映されなかったようです。多分何度も投稿されただろうと思いますが、全て受け入れられていました。画面で見えなかっただけのようです。お騒がせしました。というかJugemはもっとしっかりして欲しい…。
せぬひまのワークショップも楽しそうですね!間近で演奏を聴けるなんて素敵です。和室のような小さな空間だったら圧倒されてしまいますよね。
一緒にお茶しながらお話できるというのもうらやましいです!
>からなしさん
もっぴはいつもあんなです(笑)予想通りですよ(^o^)
茂山家のトークを聞いたのは初めてですかー!ちょっと意外でした~。いっぺさんは結構ツッコミ派で、もっぴは一人可笑しな路線をいっちゃいます。要は目立ちたがりなんですけど。
私は一列目の、通路を挟んだ左ブロックでした。確かにセンターブロックの前のほうでおしゃべりしていらっしゃる方がいましたが、残念ながら私ではないです~。
ロビーでの遭遇は、友達が教えてくれたからです(^^;感謝感謝です。
>調緒さん
こんにちは!いろいろと大変だったようですね。今は具合は大丈夫ですか?
調緒さんも観に行かれてたんですね~
レクチャーのときはさすがにメモを取っていました。聞いただけでは覚えられないと思って(^^;
私も、茂山家のレクチャーはよく聞いたことがあっても、能楽師さんのお話は本当にめったに聞いた事が無かったので貴重な体験でした。やっぱり出演者のお話を聞いて、その人となりを感じた上で演奏を聴いたり演技を観たりすると、だいぶ思い入れが強くなりますよね。こういう機会は本当にありがたいです。
そして
三地は、囃子の曲の中に一番よく出てくると広忠さんが仰っていて、確かにその後演じられた「鞍馬山」にも何回か出てきました。
譜を見ると簡単そうなんですけど、やっぱり難しいですねぇ。大小お互いが息を合わせて間を作らないといけないからかなぁと思いました。
>舞妓さん
この日記を書いているJugemが調子が悪く、投稿されたコメントがすぐに画面に反映されなかったようです。多分何度も投稿されただろうと思いますが、全て受け入れられていました。画面で見えなかっただけのようです。お騒がせしました。というかJugemはもっとしっかりして欲しい…。
せぬひまのワークショップも楽しそうですね!間近で演奏を聴けるなんて素敵です。和室のような小さな空間だったら圧倒されてしまいますよね。
一緒にお茶しながらお話できるというのもうらやましいです!
>からなしさん
もっぴはいつもあんなです(笑)予想通りですよ(^o^)
茂山家のトークを聞いたのは初めてですかー!ちょっと意外でした~。いっぺさんは結構ツッコミ派で、もっぴは一人可笑しな路線をいっちゃいます。要は目立ちたがりなんですけど。
私は一列目の、通路を挟んだ左ブロックでした。確かにセンターブロックの前のほうでおしゃべりしていらっしゃる方がいましたが、残念ながら私ではないです~。
ロビーでの遭遇は、友達が教えてくれたからです(^^;感謝感謝です。
>調緒さん
こんにちは!いろいろと大変だったようですね。今は具合は大丈夫ですか?
調緒さんも観に行かれてたんですね~
レクチャーのときはさすがにメモを取っていました。聞いただけでは覚えられないと思って(^^;
私も、茂山家のレクチャーはよく聞いたことがあっても、能楽師さんのお話は本当にめったに聞いた事が無かったので貴重な体験でした。やっぱり出演者のお話を聞いて、その人となりを感じた上で演奏を聴いたり演技を観たりすると、だいぶ思い入れが強くなりますよね。こういう機会は本当にありがたいです。
そして
なんでコメントが切れてるんだ!?
>調緒さん
そして、お知らせありがとうございます。素敵な会ですね!
これって誰でも観に行けるんでしょうか?入場料とか、事前申し込みとか必要なのでしょうか。
梅若六郎師のサイトを観ても分からなかったので…
ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします!
>調緒さん
そして、お知らせありがとうございます。素敵な会ですね!
これって誰でも観に行けるんでしょうか?入場料とか、事前申し込みとか必要なのでしょうか。
梅若六郎師のサイトを観ても分からなかったので…
ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします!
こんばんは!早速お返事をいただきありがとうございます!
レポ2も読ませていただきました。
観に行かれなかった方もきっと、思わず映像が目に浮かんでしまう、ステキなレポートですね。私もそうだった、そうだったと、あの映像が再び浮かんできました!
狂言には似たような内容のものもありますね。「六地蔵」はまた観ていませんが、一昨日、「ござる乃座」で観た「金津地蔵」(和泉流)も「仏師」とほとんど同じでした。地蔵に仕立てられた子(野村裕基くん)が、健気で、とても愛らしかったです。
「こころみの会」のご案内が不十分でごめんなさい。
下記アドレスで、番組がわかります。(多分・・・)
http://www.noh-umewaka.com/picture/05_04_15.jpg
○第4回 緑桜会「こころみの会」○
日時:4月15日(金)午後4時開演
場所:梅若能楽院会館(東中野)
出演:大倉源次郎さん、亀井弘忠さん、助川治さん、松田弘之さん。主催が山村庸子さん、梅若六郎さんもご出演されます。
料金:4000円(全席自由)
お申込み、お問合せ:山村庸子さん(緑桜会)
:FAX03-3392-3267
事前にファックスで、お問い合わせ、お申し込みされるのが良いと思います。
お囃子を主とした会で、「能」「狂言」の演目はありませんので、お気をつけくださいませ。
レポ2も読ませていただきました。
観に行かれなかった方もきっと、思わず映像が目に浮かんでしまう、ステキなレポートですね。私もそうだった、そうだったと、あの映像が再び浮かんできました!
狂言には似たような内容のものもありますね。「六地蔵」はまた観ていませんが、一昨日、「ござる乃座」で観た「金津地蔵」(和泉流)も「仏師」とほとんど同じでした。地蔵に仕立てられた子(野村裕基くん)が、健気で、とても愛らしかったです。
「こころみの会」のご案内が不十分でごめんなさい。
下記アドレスで、番組がわかります。(多分・・・)
http://www.noh-umewaka.com/picture/05_04_15.jpg
○第4回 緑桜会「こころみの会」○
日時:4月15日(金)午後4時開演
場所:梅若能楽院会館(東中野)
出演:大倉源次郎さん、亀井弘忠さん、助川治さん、松田弘之さん。主催が山村庸子さん、梅若六郎さんもご出演されます。
料金:4000円(全席自由)
お申込み、お問合せ:山村庸子さん(緑桜会)
:FAX03-3392-3267
事前にファックスで、お問い合わせ、お申し込みされるのが良いと思います。
お囃子を主とした会で、「能」「狂言」の演目はありませんので、お気をつけくださいませ。
>調緒さん
レポ2も読んでくださってありがとうございます~お役に立てて幸いです。
こころみの会の詳細、ありがとうございます!
この情報を投稿版に掲載させていただきたいと思います。
ああ~ぜひ行きたい!けどこの時間はちょっと早すぎる…
調緒さんは行かれるんでしょうか。感想をお待ちしています!
レポ2も読んでくださってありがとうございます~お役に立てて幸いです。
こころみの会の詳細、ありがとうございます!
この情報を投稿版に掲載させていただきたいと思います。
ああ~ぜひ行きたい!けどこの時間はちょっと早すぎる…
調緒さんは行かれるんでしょうか。感想をお待ちしています!
初めましての方はぜひ自己紹介を。
トラックバック
記事内容に全く関連のないトラックバックは断り無く削除します。
この記事にトラックバックする: